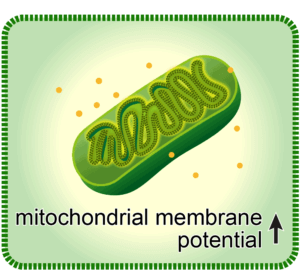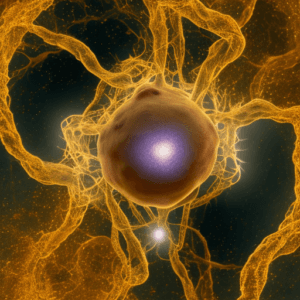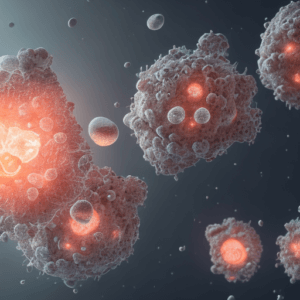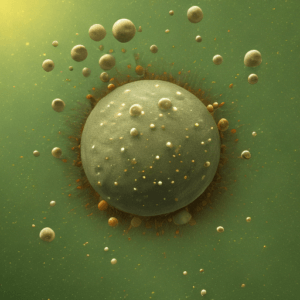「腸内フローラのバランスの乱れ」が「慢性炎症の元」で「万病の元」②
前回の腸内フローラのバランスが乱れることによって、腸だけでなく全身の病気が引き起こされるという話に驚かれた方も多いと思いますので、もう少し説明します。
下の図の右側の①が正常な状態です。(symbiosisは共生という意味です。 ヒトと腸内細菌が仲良く共生している状態です)
左が②、右が①

①の時は、腸内細菌が「腸のエネルギーになる短鎖脂肪酸」をつくっているので、腸の細胞同士はしっかり結合していて、「腸内細菌がつくる悪い物質」は体のなかに入ることができません。
ところが、②の「腸内フローラのバランスが乱れた状態」になると、(dysbiosis:ディスバイオシス かっこいいけど言いにくい言葉)
腸内細菌が短鎖脂肪酸をつくることができないので、腸の細胞が更新するために必要なエネルギーが足りなくなり、細胞は更新できないので、腸の細胞同士は「スカスカ状態」になっています。
このような「スカスカ状態」になると、「腸内細菌がつくった悪い物質」や「菌」のように体の中に入ると体に悪い影響を与えるようなものが体の中にはいってしまいます。
体に悪い物質がはいると、体は自分を守るために防衛体制になって、常に戦っている状態(慢性炎症)になり、その結果様々な病気にかかるということが最近の研究でわかってきたのです。
大野先生のレビューはこちらです。
大野, 亜鉛栄養治療, 8 , 50-57, 2018.
続きはこちら→ https://arterio.co.jp/2019/07/15/dysbiosis-3/
補足ですーーーーーーーーーーーー
腸内細菌が短鎖脂肪酸をつくれるようにするには、腸まで届く主食に含まれている難消化性デンプン(腸内細菌の餌と短鎖脂肪酸の元)が必要です。食物繊維ではありません。
(しつこく⑪くらいまで書いています)
短鎖脂肪酸については
短鎖脂肪酸と腸内細菌のネットワーク ①(短鎖脂肪酸の働きについて)(③まであります)