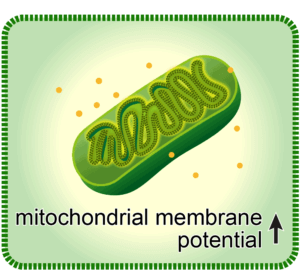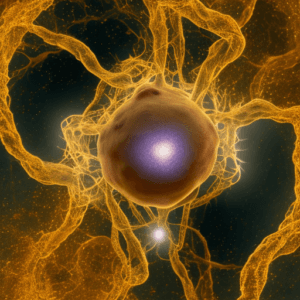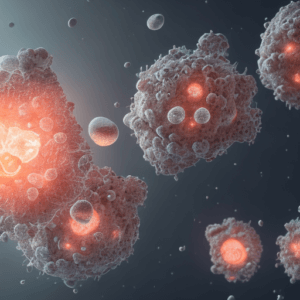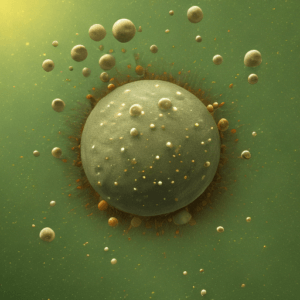多くの人が悩んでいるオナラの問題を独自に解明!
オナラの原因は呑気といわれますが、本当なのでしょうか
このブログでは、オナラが出る仕組みについて、他の動物との比較や、進化の過程を通して考えてきました。
オナラというのは、一般には空気をのむ「呑気(どんき)」が原因といわれてきました。
病院でも、お腹が張って苦しいと訴えても、特に異常は見当たらないので正常です。ストレスですから気にしないようにしましょう、と簡単に片づけられてしまいます。
オナラで困っている人は非常に多く、ストレスをためないようにと言われても困ってしまいますね。ではどうすればよいのでしょうか。
何でもストレスのせいにしてはいけない!
お腹が張ることを腹部膨満感といいますが、多くの人が困っているにもかかわらず、腹部膨満感の原因はわかっていません。それでストレスによる呑気(空気をのむこと)が原因とされてきました。
オナラは死ぬような病気でもないと考えられてきたので、これまでは「気のせい」で済まされてきたのです。
そもそも医学は形態学が中心ですので、医者が目で見て、血液などの検査をして、X線などの画像を撮ってみて、異常が発見できなかったら、それは病気ではない、つまり気のせいということになります。
気のせいでは患者は納得しないので、それはストレスのせいです、といいます。
日本の研究者も参加して国際的な学会でローマ基準という診断基準がつくられています。オナラ診断の総本山はこのローマ基準です。
過敏性腸症候群では多くの方が腹部膨満感で困っていますが、実は過敏性腸症候群にはガス型というのは診断基準では存在しないのです。

つらいオナラはどこでみてもらえるの?
ローマ基準では、原因のはっきりしない胃腸の症状(機能性消化管障害)を大きく二つに分けています。主に胃腸の上半分で起こる機能性ディスペプシア(わかりにくい!胃腸症のこと)と下半分で起こる過敏性腸症候群です。
オナラは呑気が主原因と考えているので、どちらかというと上半分(機能性ディスペプシアの方)に入れられています。
今年(2016年)発効したローマ基準の第4版(RomeⅣ)では、臓器に明らかな異常がある場合は、機能性消化管障害でなく、別(器質性障害)に分類して、過敏性腸症候群は明らかな異常がないものに限定しています。さらに腹部膨満感に関しては過敏性腸症候群の診断からは外れてしまいました。
過敏性腸症候群はストレスなどの神経症が原因で起こる消化管障害という定義が明確になったといえます。
過敏性腸症候群は、心身医学を専門とする医師が担当してきたのはこのような経緯からなのです。
診断基準にはない過敏性腸症候群ガス型
変わりつつあるオナラの診断
多くの人が悩んでいるオナラ(腹部膨満感)はいったいどこでみてもらえばいいのでしょうか。
日本には日本消化器病学会、日本消化管学会、日本神経消化器病学会などの学会があります。これらの学会が中心となって、国内での診療ガイドラインが策定され、国際学会にも参加して、ローマ基準の策定にも参加しています。
先日、札幌で日本神経消化器病学会の学術集会がありました。この学会は心身医学の立場で機能性消化管障害を研究する学会で、過敏性腸症候群についての中心的な存在です。
これまで心身医学の立場から、過敏性腸症候群の原因はストレスであると断定してきました。ところがここにきて別の原因が考えられるようになってきました。
ある会場で質問が出ました。「過敏性腸症候群のきっかけは何なのでしょうか?」
RomeⅣの刊行にも関わった有名な先生が答えました。「それは腸管バリアの破たんかもしれませんね・・・」
え~、自分の耳を疑いました。これまで過敏性腸症候群の原因はストレスだと言い張ってきた人物が・・・

異常なオナラの第二の原因、バリア機能の破たん
オナラの原因で第一に考えられるのは、小腸細菌異常増殖(SIBO)でした(→オナラが湧き出る理由は間違った食事)。
もう一つの原因がこのバリア機能の破たんです。バリア機能というのは個体を外界から守るための防御装置です。
動物では体の表面に上皮という細胞があり、内部を守っていますが、腸管内部は体の外なので、腸管にも上皮があって、バリアの役割を果たしているわけです。
このバリアが炎症などで破られることがあります。過敏性腸症候群の人は腸炎を経験していることが多いことが分かってきました 2)。
私も学生時代に2度卵にあたってひどい腸炎を経験し、そのあと過敏性腸症候群の症状が出てきました。
つまり腸炎などで腸管のバリアが破たんすると、腸管の未消化物などが大量に体内に侵入してアレルギーを引き起こす可能性があります。
バリアが突破されてアレルギーを引き起こすことは前回報告の通りです(→オナラを克服するためのアレルギー対策(その1))。
形にこだわらず、事実を受け入れる
過敏性腸症候群の人はアレルギーや腹部膨満症を併発していることが多いといいます1)。これらを別々に考えると、それらの関連性を見失います。
形にこだわって無理に分類しようとせずに、これらを総合的にとらえた方が、実態に即しています。
一口に腹部膨満といいますが、経験者の立場から言うと腹部膨満には2種類あります。
一つは発生したガスが腸内に停滞するケースで、いわゆるガスだまり。
もう一つは止めどもなくガスが湧き出るガス腹。この二つは混同されますが、メカニズムが違います。
ガスだまりはガスが移動しないためにお腹が張ってオナラが出ないので苦しい状態で、ガス腹はオナラが出て出て困る状態です。
多くの場合、ガスだまりは便秘を、ガス腹は下痢を伴います。

過敏性腸症候群は一人一人にストーリーがある
たかが「オナラ」、されど「オナラ」
実に多くの人が「腹部膨満」つまり「オナラ」で困っています。
しかしオナラに効く薬は実のところ存在しません。ガスを出やすくして、膨満感を解消するだけです。つまりガスだまりの解消にはなるようです。
オナラの原因は呑気症とされ、ストレスが原因の神経症として扱われるので、心理カウンセリングや、抗うつ薬、抗不安薬が処方されることもあります。
オナラや過敏性腸症候群の人は長い間苦しんでおり、どこに相談してもはっきりとした方針が得られないのが現状です。
「オナラ」が出るのが嫌で食物繊維を一切摂らないという人がいますが、食物繊維を摂らないとむしろオナラは悪化します。
オナラの問題を解決するために
さて結論を急がなければなりません。
過敏性腸症候群を主に二つに分けたいと思います。一つは便秘傾向で、ガスだまりが発生しやすく、腹痛を伴うことが多く、腸の形態異常も多い。
もう一つは下痢傾向で、ガス腹になりやすく、腹痛を伴い、アレルギー傾向です。
これらは複合しやすく、便秘と下痢を交互に繰り返すこともあります。
これらはそれぞれに原因があります。つまり「機能性(原因が見つからない)」ではないのです。
ガスだまりの原因は腸の機能低下で、それは長年の間違った食事の結果です。腸を育て、鍛えることを怠ったためと考えられます。
ガス腹の原因は腸のバリア機能の破たんや悪い食習慣です。
オナラの原因は一つではありませんが、共通して言えるのは腸内環境を整えることがキーだということです。

急がば回れ
オナラを出なくする便利な薬はありません。地道に体質を改善するしかないのです。
自分の性格のせいにする必要もありません。なぜならガス腹やガスだまりの原因はストレスではないからです。
まず腸内環境をよくする必要があります。腸内細菌がつくる酪酸などの短鎖脂肪酸が腸のエネルギーとなって、腸管バリアを回復させます。
そうすると腸の形態も回復し、炎症やアレルギーも収まってきて、蠕動運動が正常化します。
消化管としての機能が正常化しますので、食べたものの消化がゆっくりと進行し、発酵しやすい糖質が急に腸内細菌に出会うことがなくなります。
ガスがブクブク出るのは小腸に腸内細菌が上がってくるSIBOや、食物過敏によって糖質が未消化のまま大腸に突入することが原因と考えられます。一時的に食物過敏を示す食品を避ける必要もあります。
もう一つ大切なことは、腸の奥に届く消化しづらい食物繊維や糖質をきちんととることです。腸管は筋肉の塊のようなもので、腸管をウンチが通ることで腸管の筋肉が鍛えられて形を保ちます 3)。
まとめ
さて、ここまで長々とオナラのメカニズムについて書いてきましたが、オナラについてすべてが分かったわけではありません。
オナラで困っている人が多いにもかかわらず、解決法がない、研究している人もほとんどいないという状況の中で、自分なりに(自分を実験台として)考えてきたものです。
おかげさまで今ではすっかりとよくなっており、人生が変わったようです。
腸内環境が健全であれば、「オナラ」は湧き出ることもなく、無臭で、むしろ体に良いのです。
「オナラ」をもう少し見直してもらいって、正しくオナラと付き合うことが大切ではないでしょうか。
「オナラが臭い」、「いつもゆるくて・・・」、「週に一度しか出ない」などの関するお悩みに、Dr.リラ子をはじめとするスタッフが答えます。
腸内環境の問題は現代社会の鏡なのです。あなただけの問題ではありません。一緒に考えませんか。
(参考文献)
1) Rosario Cuomo et.al., Irritable bowel syndrome and food interaction, World J Gastroenterol., 20(27): 8837–8845 (2014)
2) 福土ら, 感染後過敏性腸症候群の概念, Jpn.J.Psychosom Med., 51, p.309−311 (2011)
3) 辰巳ら, アクチン線維は張力を感じ,コフィリンとの相互作用を介して細胞骨格の動態を制御するメカノセンサーである, 生物物理 55(4),187-191(2015)